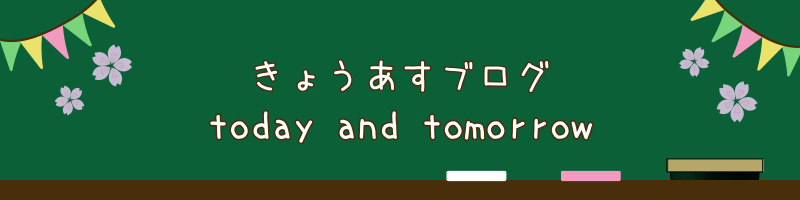みなさん、元気ですか!今日も健康志向高めていきましょう!
「そら豆って春になるとスーパーでよく見かけるけど、体にどんな良いことがあるの?」「調理や保存が難しそうで手が出しにくい…」
そんな疑問を持ったことはありませんか?実はそら豆は、春の旬ならではの栄養と美味しさが詰まった、健康にも美容にも役立つ万能食材です。
この記事では、そら豆の優れた栄養や健康効果をわかりやすく解説し、扱い方のコツやよくある疑問の解決法までご紹介します。春の食卓にそら豆を取り入れて、体の中から元気になりましょう!
そら豆の栄養がすごい!体を元気にする理由

たんぱく質とビタミンでパワーチャージ
そら豆は植物性たんぱく質が豊富で、筋肉や臓器、ホルモンの材料になります。さらに、ビタミンB1やB2、ビタミンC、カロテン、葉酸など、体に必要なビタミンがバランスよく含まれています。
ビタミンB1はエネルギー代謝や疲労回復に、B2は細胞の健康や成長に役立ちます。ビタミンCは免疫力アップや美肌効果も期待できます。
ミネラルと食物繊維で健康サポート
亜鉛・鉄分・カリウムがしっかり摂れる
そら豆は亜鉛や鉄分、カリウムなどのミネラルも豊富です。
- 亜鉛は免疫力アップや味覚の維持、肌荒れ予防に。
- 鉄分は貧血予防やエネルギー代謝に不可欠。
- カリウムは余分な塩分を排出して、高血圧やむくみの予防に役立ちます。
食物繊維でお腹スッキリ
そら豆には不溶性食物繊維が多く含まれており、腸の動きを活発にして便通を改善します。腸内環境が整うことで、免疫力アップや生活習慣病の予防にもつながります。
血管の若さを保つそら豆の成分
レシチンで動脈硬化予防
そら豆にはレシチンという成分が含まれています。レシチンは血中コレステロールの酸化を防ぎ、血管の健康維持や動脈硬化の予防に役立ちます。ビタミンB2と一緒に働くことで、さらに効果が高まります。
そら豆を美味しく食べるためのコツ
鮮度を保つには?
そら豆はさやから出すとすぐに固くなりやすいので、使う直前にさやから取り出しましょう。保存するときは、さやごと冷蔵庫に入れるのが一番です。新鮮なうちに早めに調理するのがポイントです。
簡単調理で旬の味を楽しむ
そら豆の定番は塩ゆでや焼きそら豆。さやごと焼いて中の豆を食べる方法もおすすめです。サラダやスープ、炒め物、天ぷら、パスタなど、いろいろな料理に使えます。出始めのそら豆は皮が柔らかいので、皮ごと食べても美味しいですよ。
そら豆を食べるときの注意点
食べ過ぎやアレルギーに気をつけよう
そら豆は栄養豊富ですが、食べ過ぎるとお腹が張ることがあります。また、ナッツや豆類にアレルギーがある人は注意が必要です。最初は少量から試して、体調を見ながら量を調整しましょう。
よくある質問
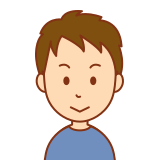
そら豆は皮ごと食べても大丈夫?
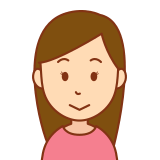
新鮮なそら豆は皮が柔らかいので、皮ごと食べてもOKです。固いと感じたら中身だけ食べましょう。
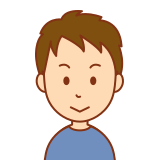
そら豆の保存方法は?
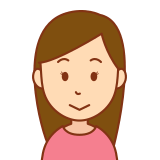
乾燥しやすいので、さやごと冷蔵庫で保存し、なるべく早めに使い切るのがコツです。
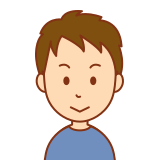
そら豆はどんな人におすすめ?
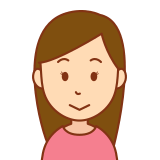
疲れやすい人、貧血や肌荒れが気になる人、便秘がちな人、高血圧やむくみが気になる人に特におすすめです。
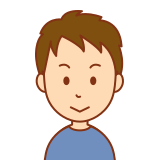
どんな料理に使える?
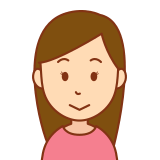
塩ゆでや焼きそら豆はもちろん、サラダ、スープ、炒め物、天ぷら、和え物、パスタなど幅広く活用できます。
まとめ:そら豆で春の健康生活を始めよう!
そら豆は、たんぱく質やビタミン、ミネラル、食物繊維、レシチンなど、体にうれしい栄養がたっぷり詰まった春の旬食材です。
鮮度や調理のポイントを押さえれば、手軽に美味しく健康効果を実感できます。
春だけの特別な味わいとパワーを、ぜひ食卓で楽しんでください。そら豆を取り入れて、体の中から元気とキレイを育てましょう!
参考ポイント
- 旬のそら豆は滋養成分が豊富
- 亜鉛や鉄分、ビタミンB群、食物繊維、レシチンなどが健康維持に役立つ
- 鮮度や調理法の工夫で、さらに美味しく&健康的に楽しめます